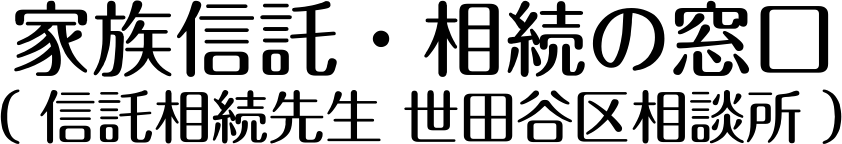相続税申告は自分でできる?手続きの流れと専門家に依頼するメリット
- 公開日:
- 更新日:
親の相続が発生したとき、「相続税申告は自分でできるのだろうか?」と悩む方は少なくありません。特に世田谷区在住の甲野家のように、高齢の親を持つ50代の子世代にとっては、自分で相続税の申告手続きを進めるべきか、それとも税理士などの専門家に任せるべきかは大きな判断ポイントになるでしょう。本記事では、相続税申告を自分で行う場合の基本的な手続きから、自力で申告する際の注意点、さらに税理士など専門家に依頼するメリットや依頼時の費用相場・専門家の選び方まで、専門家の視点も交えながらわかりやすく解説します。一度きりの大切な相続手続きですので、ぜひ参考にしてみてください。
自分で相続税申告を行う際の基本手続き
相続税の申告手続きは大きく分けて次の流れで進めます。相続発生から申告・納税までは被相続人(亡くなった方)の死亡から10か月以内という期限があるため、計画的に進めましょう。
財産目録の作成(資産・負債の洗い出し)
まず被相続人が残した財産をすべて洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産を整理して財産目録(遺産目録)を作成します。プラスの財産には現金・預貯金、株式などの有価証券、不動産(土地・建物)、貴金属・骨董品、自動車などに加え、死亡保険金や死亡退職金といった相続で受け取る金銭も含まれます。一方、マイナスの財産としては借入金などの債務残高、未払いの税金・医療費、葬儀費用などがあればそれらも漏れなくリストアップします。こうした資産・負債の全体像を把握することで正味の相続財産額が明らかになり、後の相続税額の試算に役立ちます。なお、生前に被相続人から相続人へ贈与された財産がある場合にも注意が必要です。特に死亡前一定期間内(2023年までの贈与は死亡前3年以内、2024年以降の贈与は段階的に7年以内)に行われた生前贈与や、相続時精算課税制度を適用して受け取った贈与財産がある場合は、それらも相続財産に加算しなければなりません。被相続人が残した遺言書の有無もこのタイミングで確認しておきましょう。遺言書があれば記載内容に沿って遺産分割の方針を検討します。
各財産の評価額算出と相続税額の試算
財産目録ができたら、次に各資産の評価額(相続税評価額)を算出します。現金・預金は残高がそのまま評価額ですが、不動産の場合は路線価や固定資産税評価額など相続税特有の評価方法で算出するため、市場価格よりも低い評価額となるケースが一般的です。株式や投資信託も所定の計算法に基づき評価し、プラスの財産総額からマイナスの財産総額を差し引いた正味の遺産額を計算しましょう。そして正味遺産額を相続税の基礎控除額と比較します。基礎控除額とは「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」で求められる非課税枠のことです。例えば法定相続人が配偶者と子1人の計2名なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。この基礎控除額までの遺産には相続税がかからず申告も不要です。一方、遺産総額が基礎控除額を1円でも超える場合には原則として相続税の申告・納税義務が生じます。まずは自分のケースで基礎控除額がいくらになるか計算し、遺産がその範囲内か確認しましょう。
相続税申告書の作成と提出・納税
正味遺産額が基礎控除額を超えて課税対象となる場合には、相続税額の試算を行ったうえで正式な申告書類を作成します。相続税の税率は累進課税で10%から最大55%まで段階的に上がっていきますが、実際の計算方法は法定相続分で仮計算した税額を各人に按分するなど複雑です。自分ですべて正確に算出するのは難しいため、国税庁の相続税申告書作成コーナーなどのオンラインツールも活用するとよいでしょう。申告書には相続人や財産の明細、税額の計算過程などを記載し、後述の必要書類を添付して提出します。提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。提出方法は税務署窓口への持参か郵送で行います(現在では国税庁の電子申告システム「e-Tax」でのオンライン提出も可能です)。申告期限は死亡から10か月以内であり、この期限までに申告書の提出と相続税の納付を完了させなければなりません。納税方法は基本的に現金一括納付ですが、金銭での一括納付が困難な場合には税務署の許可を受けて**延納(延長分割払い)や物納(不動産など現物で納付)**の制度を利用できる場合もあります。
必要書類の準備
相続税申告には多岐にわたる書類が必要です。以下は主な必要書類の例です。
- 被相続人および相続人の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍)
- 遺産の内容を証明する書類(預貯金の残高証明書、有価証券の残高報告書、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、生命保険金の支払通知書 等)
- 債務や葬儀費用を証明する書類(借入金残高証明書、医療費の明細や葬儀社の領収書 等)
- 遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分割方法を合意した書面。作成できていれば提出)
これらの書類をすべて揃え、相続税申告書に添付して提出します。書類不備があると手続きが遅延したり、最悪場合によっては申告期限に間に合わなくなるリスクもあるため注意しましょう。
自分で申告する場合の注意点
相続税の申告を自力で行うことは可能ですが、専門知識が必要な場面が多く慎重さが求められます。ここでは、自分で申告手続きを進める際に押さえておきたいポイントやリスクについて解説します。
複雑な財産評価・特例の適用漏れによる申告ミス
相続税には不動産の評価や各種特例の適用など専門的で複雑なルールが多数あります。例えば土地の評価では路線価図を読み取り形状や利用状況に応じた補正計算が必要です。また、適用できる特例・控除としては小規模宅地等の特例(一定要件を満たす宅地評価減)や配偶者控除、障害者控除、未成年者控除など多岐にわたります。慣れない人が独学で手続きをすると、本来使えるはずの特例を見落として「税金を払いすぎてしまう」リスクや、逆に適用条件を満たさない特例を誤って使って「本来より税額が少ない申告をしてしまう」リスクがあります。払い過ぎた税金は後から更正の請求によって取り戻せる可能性もありますが、自分でミスに気づくのは容易ではありません。一方、申告漏れや誤りがあれば後日税務署から修正申告や追徴課税を求められる場合もあります。税理士の実務上も、申告内容の誤りによるトラブル事例は少なくありません。専門知識に自信がない場合は無理をせず、早い段階で専門家へ相談することも検討しましょう。
膨大な手間と期限遵守のプレッシャー
相続税申告では前述のとおり非常に多くの書類を準備しなければなりません。例えば戸籍を集めるだけでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得する必要があり、本籍地が複数にわたる場合は各役所へ請求を行う手間がかかります。不動産が複数の市区町村にまたがっていれば、それぞれの自治体で固定資産評価証明書を取り寄せる必要もあります。さらに遺産分割協議や財産評価にも時間を要するため、10か月という申告期限は意外とあっという間です。仕事や家庭と並行してこれらの手続きを進めるのは大きな負担となりがちで、精神的なプレッシャーを感じるでしょう。こうした事務作業や期限管理に追われるあまり、本来の悲しみの整理やご家族のケアに十分な時間を割けなくなる恐れもあります。
書類不備による手続き遅延・トラブル
提出書類に不備や漏れがあると、税務署から補正を求められたり受理されないケースもあります。例えば相続人全員の署名押印が揃っていない遺産分割協議書や、必要な添付書類が欠けている申告書は受理されず、結果として期限内に正しく申告できない事態につながりかねません。また、申告内容に関して税務署から問い合わせ(「お尋ね」)が届くこともありますが、自力で対応するには負担が大きいでしょう。税理士の立場から言えば、相続税申告は一度提出したら原則修正がきかないため、少しでも不安があれば専門家を頼るのが安全です。
税理士など専門家に依頼するメリット
相続税申告を専門家(税理士など)に依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは主な利点を解説します。自力申告と比較してどんな利点があるのか確認し、ご自身の状況と照らして検討してみましょう。
煩雑な作業を任せられる安心感
財産目録の作成や申告書類の作成といった煩雑な作業を専門家に一任できるため、相続人の事務負担が大幅に軽減されます。特に平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくい方にとって、代行してもらえる安心感は大きいでしょう。また、税務署とのやり取りや問い合わせ対応も税理士が代行してくれるため、ご自身が窓口対応に追われる心配もありません。専門家に任せることで精神的負担が和らぎ、本来やるべき葬儀や諸手続きに集中できます。
適切な節税策と正確な申告
税理士は相続税申告のプロとして、豊富な知識と経験に基づいて最適な節税策を提案してくれます。不動産評価や適用可能な特例の有無なども漏れなく検討し、本来受けられる控除を逃さず反映してくれます。例えば土地の評価減につながる要素(不整形地や崖地、貸宅地など)があれば見逃さず評価額に反映し、結果として相続税の軽減が期待できます。また複雑な税額計算も正確に行われるため、申告ミスによる追徴リスクを避けられます。税理士の実務経験上も、専門家が関与することで数百万円単位で税額が下がったケースも珍しくありません。適切な節税と正確な申告によって、相続人としての金銭的・心理的な安心感が得られるでしょう。
スケジュール管理と迅速な対応
相続発生から申告までのスケジュールを税理士が管理し、期限内完了に向けてリードしてくれます。例えば税務署から6ヶ月経過時点で届く「相続税申告のお知らせ」に対しても、税理士に依頼していれば必要な対応を助言してくれます。万一期限ギリギリで遺産分割協議がまとまらない場合なども、法定相続分での一旦申告や延納申請など適切な手続きを案内してくれます。プロのサポートがあることで、時間管理の不安も軽減されるでしょう。
第三者の冷静なサポート
相続手続きでは、親族間の話し合いや調整において感情的な問題が生じることもあります。税理士等の専門家に入ってもらうことで、中立的な立場から冷静なアドバイスを受けられるのもメリットです。家族だけでは決めにくかった財産分割や納税方法についても、専門家の意見を参考にすることで合意形成がスムーズになるケースがあります。手続きの進行状況を逐一報告してもらえるため、遠方に住む相続人がいる場合でも安心感が得られるでしょう。
これらのメリットに加え、専門家に依頼することで「この手続きで本当に合っているだろうか」という不安から解放されるのも大きな利点です。一度きりの相続手続きを確実に終えたい方にとって、経験豊富な税理士のサポートは心強い味方となります。
専門家に依頼する際の費用と選び方
最後に、相続税申告を税理士に依頼する場合の費用相場や専門家選びのポイントについて説明します。費用面と依頼先の見極め方を理解し、納得できる専門家選びに役立ててください。
税理士に依頼する場合の費用相場
相続税申告を税理士にお願いするときに気になるのが費用(報酬)です。一般的に税理士への相続税申告業務の報酬は「遺産総額の0.5~1%程度」が相場と言われています。例えば遺産総額が1億円であれば報酬は約50万~100万円、5,000万円なら25万~50万円ほどが目安です。ただし、不動産が多く評価に手間がかかる場合や、相続人が多数いて手続きが複雑な場合、あるいは税務調査対応まで含めて依頼する場合などは追加料金が発生することがあります。また、遺産総額が少額でも最低料金として一定額(20~30万円程度)を設定している事務所も多く、遺産規模に関わらず最低限これくらいの費用は見込んでおいたほうがよいでしょう。
費用の支払い方法については、相続人間で誰が負担するか事前に話し合っておくと安心です。一般的には相続財産から税理士費用を差し引き、残りを相続人で分配する形(つまり相続財産全体で負担)をとるケースが多いですが、各相続人が按分割合に応じて負担する方法などもあります。揉めないよう、依頼前に負担方法を決めておくことをおすすめします。
専門家(税理士)の選び方と注意点
相続税申告の依頼先を選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう。
- 相続税の実績が豊富な税理士か – 税理士にも得意分野があります。相続税申告の経験が豊富な税理士事務所であれば、スムーズに対応してもらえる可能性が高いです。ホームページや紹介などで相続関連の実績を確認したり、「相続専門」「資産税専門」などの謳い文句がある事務所を選ぶのも一つです。
- 料金体系が明確か – 契約前に見積書を出してもらい、報酬の内訳や追加料金の条件をしっかり確認しましょう。明瞭な料金体系でないまま契約すると、後から「聞いていなかった追加費用」が発生する恐れがあります。特に税額を減らせた場合に成果報酬(減額分の○%)を設定している事務所もありますが、人によっては割高になるケースもあります。最初の問い合わせや無料相談の段階で不明点は遠慮なく質問し、納得のいく価格か見極めることが大切です。
- 相性やコミュニケーション – 相続税の申告業務は内容の濃い相談が必要となります。税理士との相性や、こちらの質問に対する説明の分かりやすさも重要なポイントです。初回相談で「この人なら信頼できそう」「質問しやすい」と感じられるか、直感も含めて判断すると良いでしょう。世田谷区で相続に強い税理士を探す場合、地域の相談センターや知人の紹介、自治体主催の相続セミナー講師などから探してみるのも有効です。
なお、専門家に依頼すべきか悩んでいる段階であれば、まず初回無料相談を利用してみるのも一案です。多くの税理士事務所は初回の相談を無料または低額で実施しています。相談してみて自分でも対応できそうか、プロに任せたほうが良さそうか判断材料を得ると良いでしょう。
まとめ(自分で申告するか専門家に任せるか)
総じて、「費用を節約してでも自分でやり遂げたいか」それとも「費用をかけても安心を買いたいか」という軸で考えると判断しやすくなります。相続税申告はやり直しのきかない一度きりの手続きです。不安が大きい場合には無理をせず専門家に相談し、納得のいく形で大切な相続手続きを完了させましょう。
相続税のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
本記事では相続税申告の基本的な流れや専門家に依頼するメリットについてご紹介しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、家族信託や相続に関する初回無料相談を承っております。相続税の申告や対策について専門家の意見を聞きたい方は、お気軽にお問い合わせください。