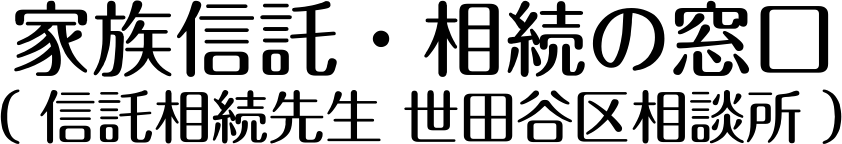相続税申告は誰に必要?基礎控除額と申告期限、手続きの流れ
- 公開日:
- 更新日:
高齢の親を持つ50代の子世代に向けて、相続税の申告義務が発生する条件や基礎控除額の仕組み、申告期限と手続きの流れについて、専門的な内容をできるだけ平易に解説します。相続税の申告が必要か迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続税申告が必要となるケース(申告義務の有無)
相続が発生したとき、まず相続税の申告が必要かどうかを判断することが重要です。相続税の申告義務が生じるか否かは、遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額以内の遺産であれば相続税はかからず申告不要ですが、超える場合はたとえ税額がゼロでも申告が必要となることがあります。ここでは基礎控除額の計算方法や法定相続人の数による影響、配偶者控除(配偶者に対する税額軽減)の効果について解説します。
相続税の基礎控除額の計算方法と適用範囲
基礎控除額とは、各相続に共通して認められる非課税枠のことで、相続税法で定められています。現在の基礎控除額は次の計算式で求めます:
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円というように、相続人の人数に応じて非課税枠が増加します。この基礎控除額までの遺産には相続税がかからず、申告も不要です。
注意すべきは、この計算に用いる「法定相続人の数」には実際に相続放棄した人や代襲相続が発生した場合の代襲者も含めてカウントできるケースがあることです(養子については控除対象となる人数に上限があります)。正確な法定相続人の数を把握することで、自分のケースの基礎控除額を正しく算出できます。遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税の申告・納税は一切不要です。
しかし、土地や家など不動産を所有している場合は評価額の見積もりが難しく、思ったより遺産額が基礎控除を上回るケースもあります。また生命保険金には「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠があるなど、基礎控除額以外にも複数の控除制度が存在します。そうした他の控除や特例を適用して税額がゼロになる場合でも、一旦遺産総額が基礎控除額を超える可能性があれば申告は必要になる点に注意しましょう。例えば生命保険金の非課税枠や障害者控除、未成年者控除などを使って最終的に税額がゼロになるケースでも、一度は基礎控除額超の財産を取得しているため申告義務が生じます。
相続税申告が必要となる具体的なケース
遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要です。例えば、遺産総額が5,000万円で法定相続人が子2人(基礎控除額4,200万円)の場合、遺産が基礎控除を上回っているので相続税申告をしなければなりません。一方、遺産総額が3,000万円で相続人が子1人(基礎控除額3,600万円)の場合は基礎控除内に収まっているため申告不要です。このように、ご自身の家庭の遺産規模と法定相続人の人数を踏まえて、まず申告義務の有無を確認しましょう。
また、相続税には配偶者に関する大きな特例があります。被相続人の配偶者が相続で取得した財産には、最大1億6,000万円まで相続税がかからない「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という制度です。したがって、配偶者が全財産を相続した場合などは相続税額がゼロになることも多いです。しかし、繰り返しになりますが相続税額がゼロでも申告が必要なケースがあります。遺産総額が基礎控除額を超えている場合には、配偶者控除などで最終的に税額がゼロになる場合でも申告書の提出義務がありますので注意してください。
相続税申告の期限と手続きの流れ
相続税申告が必要な場合、申告期限(被相続人の死亡から10か月以内)を厳守して手続きを進める必要があります。ここでは申告期限の重要性と、実際に申告までにどのような手順を踏むべきか、その一般的な流れについて解説します。また、やむを得ず期限までに納税が困難な場合に利用できる延納制度や、期限遅れによるリスクについても説明します。
申告期限(被相続人の死亡から10か月以内)の重要性
相続税の申告期限は死亡から10ヶ月以内です。例えば1月15日に亡くなった場合、申告期限はその年の11月15日となります。10ヶ月という期間は一見長いようで、遺産整理にはあっという間に過ぎてしまうので注意が必要です。特に不動産の評価や相続人間の調整に時間がかかるケースでは、早め早めの行動が求められます。
この申告期限と納期限は同日となっており、納税まで完了してはじめて正式な手続き完了となります。スケジュール感としては、死亡から6ヶ月程度経過すると税務署から「相続税申告のお知らせ」や「お尋ね」の文書が届くことがあります。これは「そろそろ申告期限が近いですが大丈夫ですか?」という確認の意味合いで送られるものです。こうした通知が届く頃までに、戸籍集め・財産調査・評価・遺産分割協議・申告書作成とやることが盛りだくさんです。慌てず着実に進めるには、専門家(税理士)に相談することも検討すべきです。自力で対応する場合でも、本記事で挙げた必要書類リストを参考に、漏れなく資料を集めてください。不明点があれば税務署や専門家に遠慮なく問い合わせましょう。
申告期限に遅れそうな場合は、延納制度を活用することも選択肢です。ただし延納を利用するには、延納申請期限までに所定の手続きをとること(申告期限と同じく死亡から10ヶ月以内に延納申請書を提出)、相続税額が10万円を超えること(延納は税額が少額の場合認められません)、金銭一括納付が困難な事由があること(例えば相続財産の大部分が不動産で、すぐに売却して納税資金を用意できない場合)といった条件を満たす必要があります。
延納が認められると、納税を分割(年賦)払いにすることができますが、その間は所定の利子税がかかります。また、納税額に見合う担保の提供が必要になるケースもあります。なお、相続財産の中に現金や有価証券など換金しやすい資産が一定額以上あると延納は許可されないこともあるため、事前に専門家と相談しながら条件を確認しましょう。
申告手続きの一般的な流れ
申告期限までにやるべき一般的な流れをまとめると、次のようになります。
- 相続人の確定 – 戸籍謄本の収集などにより法定相続人を確定します。相続放棄や認知など特殊なケースがある場合も、この時点で手続きを進めます。
- 財産目録の作成 – 前述のようにプラス・マイナスすべての財産を洗い出して一覧にまとめ、概算の遺産総額を把握します。
- 遺産分割協議 – 相続人全員で遺産の分け方を話し合います。期限までに分割がまとまらない場合は、法定相続分で一旦申告・納税し、後日分割が決まってから修正申告することも可能です。
- 申告書類の作成 – 国税庁の所定様式に従って相続税申告書及び付表を作成します。申告書第一表に各相続人の納付税額を計算し、第二表以降に明細や特例適用額を記載します。不慣れな場合、前述のオンライン作成コーナーを利用すると便利です。
- 必要書類の添付 – 戸籍謄本や財産評価明細書、遺産分割協議書など必要書類を添付し、税務署に提出します。
- 納税 – 計算した相続税額を現金で納付します。現金一括納付が困難で延納を希望する場合は、申告と同時に延納申請を行います。
上記の手順を踏み、申告期限(死亡から10か月以内)を必ず守りましょう。期限を過ぎると、次に述べるような延滞税や加算税といったペナルティが課されることになります。
申告しなかった場合のペナルティ
相続税の申告をしなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。期限に遅れてしまった場合も含め、代表的なものを紹介します。
- 延滞税 – 納付すべき税金を期限までに納めなかった場合にかかるペナルティで、いわば遅延利息です。延滞した期間に応じて日ごとに課され、遅れれば遅れるほど金額が増えます。延滞税の年率は納付遅延期間や年度によって異なりますが、金融機関の貸出金利より高めに設定されており、負担が大きくなります。
- 無申告加算税 – 期限内に申告しなかった場合に課される罰則税です。自主的に期限後申告をした場合は本来の税額の5%、税務署から指摘されて申告した場合は10~15%程度(調査通知後は原則15%)が加算されます。悪質な無申告があった場合は最大20%まで加算されることもあります。
- 重加算税 – 申告において故意の隠蔽や仮装があった場合に課される非常に重い加算税です。不正が発覚すると35~40%もの加算税が本税に上乗せされる可能性があります。例えば財産を一部意図的に申告漏れしたようなケースでは重加算税の対象となりえます。最悪の場合、刑事告発され罰金や懲役といった刑事罰に至るケースも皆無ではありません。
さらに、無申告や遅延があった場合には税務調査が実施される可能性が高まります。その際、仮に申告していれば適用できたはずの特例(例:小規模宅地等の特例など)が、期限内申告でないことを理由に適用を認められないリスクもあります。無申告で放置していると税務署側も悪質とみなして厳しく対応するため、結果的に本来よりも重い税負担を負う羽目になりかねません。
以上のことから、相続税申告は期限内に正確に行うことが何より重要です。世田谷区の甲野家でも「もし申告しなかったらどうなるんだろう」と不安に思ったそうですが、やはり延滞税や加算税で余計な負担を背負うリスクを避けるため、期限内申告を徹底することが大切です。申告が必要な場合はスケジュールに余裕をもって準備を進め、場合によっては専門家の助力も得ながら、円満に相続手続きを完了させましょう。
相続税のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
本記事では相続税申告が必要となる条件や申告期限内に進めるべき手続きの流れについてご紹介しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、家族信託や相続に関する専門相談を初回無料で承っております。相続税申告の要否判断や具体的な手続きについて不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。