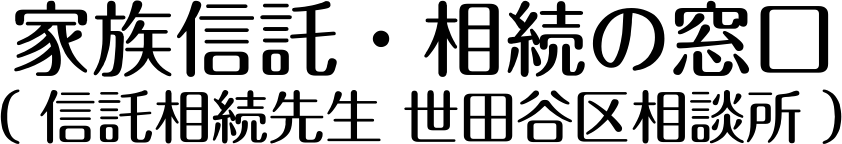生命保険や不動産活用は相続税対策になる?その他の節税策と注意点
- 公開日:
- 更新日:
相続税の負担を軽くする方法には、生命保険の活用や不動産への資産組み換えなど様々な選択肢があります。それぞれの対策の仕組みやメリットだけでなく、注意すべきポイントもしっかり押さえておくことが大切です。ここでは、50代の子世代の方向けに、親の相続に備える主な相続税対策とその注意点をわかりやすく解説します。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険は相続税対策としてよく活用されます。その理由は、生命保険金には相続税法上の非課税枠が設けられており、相続人(法定相続人)が受け取る死亡保険金の一部が非課税になるからです。例えば世田谷区の甲野さんは、子ども2人への相続を見据えて終身保険に加入し、死亡保険金から最大1,000万円まで非課税で残す対策を取りました。契約形態を工夫することで所得税の非課税枠を利用し、相続税負担を軽減できる場合もあります。以下、生命保険を使った具体的な節税ポイントを見ていきましょう。
死亡保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)の活用
被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入しており、相続人が死亡保険金を受け取った場合には、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税になる仕組みがあります。この非課税枠は、相続人全体で受け取った保険金に対して適用され、たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら最大1,500万円までの死亡保険金が相続税の課税対象から除かれます。受取人が相続人でない場合(例:孫が受け取るなど)はこの非課税枠は使えませんので注意が必要です。
具体例:
法定相続人が子ども2人の場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。このケースで死亡保険金800万円を子ども達が受け取った場合、1,000万円の枠内に収まるため全額が非課税になります。一方、現金で800万円を遺した場合は基礎控除枠を超えればその全額が課税対象となる可能性があります。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外で直接受け取れるため、迅速に葬儀費用や納税資金に充てられる点でも有用です。
契約者(保険料負担者)を工夫して所得税非課税枠も活用
生命保険金に係る税金は、「誰が保険料を負担したか」と「誰が受取人か」によって課税方式が変わることをご存知でしょうか。典型的な契約では、被相続人自身が保険料を支払い、相続人が死亡保険金を受け取るため相続税が課税されます。しかし、保険料負担者と受取人を同一人物(相続人本人など)にする契約形態にすれば、死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。一時所得には年間50万円の特別控除があり、さらに課税対象額はその利益部分の1/2だけです。結果として、相続税課税の場合よりも低い税負担で済むケースがあります。
具体例:
子どもが契約者(保険料負担者)となり、親を被保険者・子どもを受取人とする保険に加入したケースを考えます。仮に子どもが支払った保険料総額が500万円、死亡保険金が1,000万円だった場合、所得税の計算上は受取額1,000万円-支払保険料500万円-特別控除50万円=450万円が一時所得となります。その1/2の225万円が課税対象となり、受取額全体に相続税が課税される場合と比べて大幅に負担を抑えられます。この方法では死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は使えなくなるものの、所得税の特別控除を活用する形で節税効果が得られるわけです。ただし、この契約形態では子ども自身が保険料を払い続ける必要があります。親が子に保険料を渡して代理で払わせているだけでは、その資金移動が贈与とみなされるリスクがあります。制度を使う際はこうした契約設計上の注意点も踏まえ、専門家と相談して適切かどうか判断しましょう。
不動産の活用による相続税対策
現金・預金などのまま遺産を残すより、不動産を活用することで相続税評価額を下げられる場合があります。これは、不動産の相続税評価額(課税評価額)は市場価格に比べて低く算定されることが多いためです。さらに、賃貸用の不動産にすれば利用や処分に制限がかかる分、評価額が一層引き下げられる特例もあります。ここでは、現金を不動産に組み換える方法や賃貸物件・小規模宅地等の特例を活用した評価減について、具体例を交えて説明します。
評価額の低い不動産への資産組み換え(現金→不動産)
現金は額面どおり100%の評価となりますが、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づいて評価されるため、市場価格より低い評価額になるケースが一般的です。そのため、生前に現金・預金を使って不動産を取得したり建築したりすることで、相続税の計算上の財産評価額を圧縮できる可能性があります。
具体例:現金1億円を都市部の土地に組み換えた場合、その土地の相続税評価額は「路線価×地積」で計算され、路線価は公示地価の80%程度が目安となります。つまり、1億円相当の土地でも評価額は約8,000万円に抑えられる計算です。さらに1億円で建物(賃貸マンション等)を建築した場合、建物の評価額は固定資産税評価額となり、建築費のおよそ60%程度(約6,000万円)になることもあります。結果として、1億円の現金を土地に変えれば評価額8,000万円ほどに、建物に変えれば約6,000万円に圧縮できるわけです。老朽化したアパート等を建て替えて新築不動産にするケースでも、建物評価額は建築費ベースの算定となるため、現金を投下した金額より低く評価される効果が期待できます。ただし、不動産取得にはコストがかかり、相続後に売却しにくい(流動性が低い)点もあるため、この後述べる注意点に留意しましょう。
賃貸物件や小規模宅地特例の活用で評価減を図る
不動産を賃貸用として活用すると、さらに相続税評価額を下げることができます。賃貸物件では、土地については「貸家建付地」評価が適用され、一般に更地評価より約2割減額(評価額の約8掛け)されます。建物についても「貸家」評価として評価額が3割減額されます(自用の建物と比べて賃借人がいる分だけ価値が低いとみなされるため)。例えば、1億円で新築した賃貸アパートの場合、上記の土地・建物の減額を反映すると相続税評価額が約4,200万円になるケースもあります。実際に税理士の試算でも、借入を活用して賃貸アパートを建築したことで正味の財産(課税対象額)が約6割減少した例が報告されています。
また、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用・貸付用の土地については、「小規模宅地等の特例」を適用することで大幅な評価減が可能です。たとえば、同居の親族が引き継ぐ自宅の宅地であれば330㎡まで80%減額、貸付事業(賃貸)の宅地であれば200㎡まで50%減額といった具合に、一定面積まで評価額を圧縮できます。実際に、小規模宅地等の特例を使うと土地評価額が最大で8割減になるため、相続税額が大きく下がります。例えば、被相続人の自宅土地(評価額8,000万円・面積400㎡)では、特例適用後の評価額は約2,720万円と3分の1以下に圧縮できたケースがあります。賃貸物件を所有していた場合も、要件を満たせば貸付事業用宅地として50%評価減の対象になります。
注意点:
ただし、不動産取得には各種費用(仲介手数料・登録免許税・不動産取得税など)がかかり、賃貸経営には空室リスクや建物の維持管理費も伴います。新築によって賃貸収入が向上し相続後の収益性が増す一方で、手元資金を投下した分が将来的に資産を再び膨張させる可能性もあります。税理士の立場では、不動産を使った節税策は効果が大きい反面、流動性や経営リスクにも目を向けて総合的に判断すべきだと助言しています。
二次相続まで見据えた相続税対策
相続税対策を考える際には、一次相続(最初に親の一人が亡くなったとき)だけでなく、配偶者が亡くなった後の二次相続まで踏まえて計画を立てることが重要です。一次相続では配偶者に対する「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」により、配偶者が取得した財産について最大1億6,000万円まで相続税がかからない特例があります。しかし、配偶者に多くの財産を残しすぎると、いざその配偶者が亡くなった二次相続で相続人(子)のみで多額の遺産を相続することになり、結果的に高い税率が適用されて相続税負担が増えてしまうケースが少なくありません。ここでは、一次相続・二次相続をトータルで捉えた相続税対策の考え方を紹介します。
一次・二次の税負担を平準化する資産配分
ポイントは、一次相続と二次相続の税負担をトータルで平準化することにあります。具体的には、一次相続の段階で子どもにもある程度の財産を相続させておくことで、配偶者一人に財産が集中するのを避けます。こうすることで、二次相続時の相続財産総額を抑え、高い税率が適用されるのを防ぐ効果が期待できます。
具体例:被相続人の遺産総額が1億円、相続人が配偶者と子1人というケースを考えます。極端に一次相続で配偶者に全額を相続させると、二次相続時に子が1億円を相続する形となり、高い累進税率が適用されます。試算では、一次・二次通算の相続税額は約1,220万円に達します。そこで一次相続で配偶者5,000万円・子5,000万円ずつ相続すると、二次相続時の課税遺産は5,000万円-基礎控除3,600万円=1,400万円程度となり、税額も約160万円で済みます。結果、一次と二次を通じた総相続税額は約545万円となり、配偶者に全額相続させた場合より半分以下の負担で済むことがわかります。このように、一次と二次を通じた最適分割を検討することで、トータルの税額を大きく減らせる可能性があります。
生命保険の活用で二次相続時の非課税枠を確保
二次相続まで見据えた生命保険の活用も有効です。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、一次相続・二次相続それぞれで適用できます。したがって、夫婦それぞれが生命保険に加入しておくことで、一次相続発生時と二次相続発生時の両方で非課税枠を最大限活用することが可能です。例えば母親が自分を被保険者とする終身保険に加入し、受取人を子どもにしておけば、母親死亡時(二次相続時)には子どもが再び500万円×法定相続人の数(子どもが2人なら最大1,000万円)の非課税枠を利用できます。こうした受取人設定や契約者・被保険者の組み合わせを工夫すれば、一次相続・二次相続それぞれのタイミングで生命保険の非課税枠をフルに活かすことができます。ただし、高齢になってからの保険加入は保険料が割高になったり、健康状態によっては加入自体が難しいケースもあります。保険契約は長期的な視野が必要となるため、家族構成や資産状況に応じて早めに検討しておくことが望ましいでしょう。
専門家に相談してみよう
相続税対策はご家庭の状況によって取るべきアプローチが異なります。税理士など専門家に相談すれば、「何もしなかった場合の相続税はいくらになり、どんな対策をすればどれだけ減らせるか」といった具体的な数字のシミュレーションを提示してもらえます。場合によっては、生命保険や不動産だけでなく、生前贈与(年間110万円の基礎控除枠の活用や住宅取得資金贈与の非課税特例など)を組み合わせた総合的な提案を受けられるでしょう。例えば、子や孫に対して住宅取得資金の贈与を行えば、一定の要件下で非課税(2026年12月までの時限措置)とすることも可能です。こうしたあらゆる選択肢を含め、専門家と一緒に自分たちに最適なプランを考えてみることをおすすめします。
相続税のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
本記事では生命保険や不動産の活用による相続税対策のメリットと注意点、および一次・二次相続を通じた節税策の考え方について解説しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、相続税に関するご相談はもちろん、家族信託や生前贈与、遺言作成など幅広い相続対策について専門家がアドバイスいたします。最適な相続税対策を検討したい方は、お気軽にお問い合わせください。