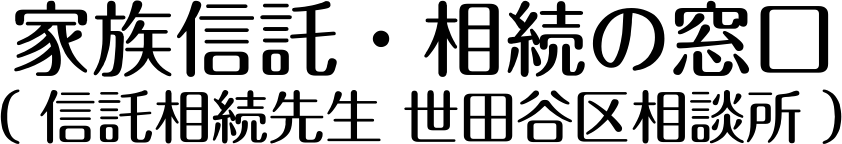相続税対策の基本:早めに知っておきたい生前対策のポイント
- 公開日:
- 更新日:
相続税対策は、高齢の親を持つ50代の子世代にとって早めに取り組みたい重要なテーマです。相続税の制度は平成27年(2015年)の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられ、これにより相続税の課税対象となるケースが増加しました。実際に相続税がかかった方の割合は亡くなられた方全体の約1割(令和5年時点で9.9%程度)に上ります。相続税の課税対象になる遺産規模に達すると、数百万円単位の税負担が生じるため、生前からの対策が欠かせません。そこで本記事では、相続税対策がなぜ必要かという理由から、知っておきたい相続税の基礎知識、生前にできる具体的な節税策の種類、そして対策の第一歩となる資産把握と専門家への相談について解説します。専門的な内容をできるだけ平易にまとめていますので、ぜひ今日からの相続税対策にお役立てください。
相続税対策が必要な理由(早めの準備の重要性)
相続税の課税対象が拡大
かつて相続税は一部の富裕層にだけ関係する税金という印象がありましたが、近年では一般の家庭にも無視できないものとなりつつあります。その背景には相続税の基礎控除額の引き下げがあります。2015年以降、相続税の非課税枠である基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小され、例えば相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)なら4,800万円が基礎控除額となりました。このため、自宅不動産や預貯金など合計で4,800万円を超える遺産がある場合には相続税の申告・納税が必要になります。基礎控除額改正前は課税対象となるのは死亡者の数%程度でしたが、現在では約1割が相続税の課税対象となっています。都市部で自宅や土地を所有している家庭や、相続人が少なく基礎控除額が小さいケースでは、特別裕福でなくても相続税が発生し得る状況です。
「生前対策」は時間を味方に
相続税対策を早めに始める最大の理由は、時間をかけることで節税効果を高められる点です。例えば後述する暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)による資産移転は、年数をかけてコツコツ行うほど大きな節税効果が得られます。一方で、相続直前になって慌てて贈与しても、被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され相続税の課税対象になってしまいます(※2024年からはこの持ち戻し期間が死亡前7年以内に延長)。早めに準備を始めれば、この「生前3年(→7年)ルール」の影響を避けつつ計画的に贈与を進めることが可能です。また、親御さんが元気なうちに対策を講じておけば、財産状況の把握や遺産分割の希望について家族で十分に話し合う時間も確保できます。早期からの生前対策は、相続税の節税だけでなく、将来の相続手続きや家族間のトラブル防止にもつながる点で重要と言えるでしょう。
相続税の基礎知識(基礎控除額・税率の仕組み)
相続税がかかる基準
相続税は、遺産総額(プラスの財産から借金や葬式費用を差し引いた正味の遺産額)が一定の非課税枠(基礎控除額)を超えた場合に、その超えた分に対して課税されます。基礎控除額は前述のとおり「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば相続税は一切かかりません。逆に言えば、遺産が基礎控除額を1円でも超えると、その超えた部分に対して相続税の申告・納税義務が生じます。まずはご自身のご家庭の場合、基礎控除額がいくらになるかを把握しておくことが大切です。
税率と課税方法
相続税の税率は一律ではなく、課税対象となる遺産の額に応じた累進課税(段階的な超過累進税率)が適用されます。具体的には、基礎控除後の課税遺産総額をいったん法定相続人ごとに法定相続分で按分して仮の各人の税額を計算し、それを実際の取得額に応じて配分するという複雑な方式で最終的な各人の相続税額を算出します。税率は課税額が大きいほど高くなり、10%から最大55%まで段階的に引き上げられる仕組みです。例えば、課税遺産総額が5,000万円程度であれば税率は一部が15%・一部が20%といった具合ですが、課税遺産総額が3億円を超えるような規模になると、その超過部分には50%以上の税率が適用されます。このように、相続税は遺産が大きいほど重い税負担となる点を押さえておきましょう。
生前にできる具体的な相続税対策のポイント
相続税対策として生前から取り組める具体策には、例えば次のようなものがあります。
年間110万円までの暦年贈与
毎年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない「暦年課税」の仕組みを利用し、長期間にわたって少しずつ財産を子や孫に移す方法です。毎年コツコツと非課税枠内で贈与を続ければ、その分相続時の遺産が減り、相続税の節税につながります。ただし注意したいのは、死亡前3年以内(2024年以降の贈与は段階的に7年以内)の贈与は相続財産に持ち戻されるというルールです。したがって、駆け込み的に多額の贈与をするのではなく、早めに贈与を開始しておくことが重要です。また、毎年同じ額を同じ時期に贈与すると「最初からまとまった額を贈与するつもりだった」と見なされ、全額に贈与税がかかるリスクがあります(定期贈与とみなされる危険)。そうならないよう、毎年の贈与額・時期はその都度決定し、贈与契約書を毎回作成して証拠を残す工夫をしましょう。
生命保険の非課税枠の活用
被相続人が生命保険に加入しており、相続人が死亡保険金を受け取った場合には「500万円×法定相続人の数」までの保険金が相続税非課税になります。例えば相続人が配偶者と子2人なら計3人で最大1,500万円まで非課税です。この制度を活用すべく、親が死亡保険に加入しておき相続発生時に保険金が下りるようにする家庭もあります。生命保険は相続税対策になるだけでなく、すぐに現金が入るため納税資金や葬儀費用に充てられるという利点もあります。また、保険契約の仕方によっては保険金を相続税ではなく所得税(一時所得)の対象にでき、所得税の特別控除(50万円)や1/2課税の優遇を受けて相続税より有利になるケースもあります。ただしこの方法では子など受取人自身が保険料を負担する必要があり、親からの仕送りで保険料を支払う形だと贈与とみなされるリスクがある点に注意しましょう。
不動産への資産組み換え
現金で持っているよりも不動産として持っていたほうが相続税評価額を低くできる場合があります。不動産の評価額は路線価や固定資産税評価額を基に計算されるため、市場価値より低めになることが多いからです。例えば現金1億円で土地を購入した場合、その土地の評価額は公示価格の約80%程度(8,000万円前後)になるケースがあります。また1億円で賃貸マンションを建てた場合、建物の評価額は建築費の60%程度(6,000万円前後)となることもあります。このように現金を不動産に換えることで、評価額ベースで資産圧縮が期待できます。さらに、賃貸物件にすれば「貸家建付地」「貸家」として土地評価額が20%減、建物評価額が30%減となる特例も受けられます。ただし不動産取得には仲介手数料や税金などのコストがかかるほか、相続後に売却しにくい(流動性が低い)デメリットもあります。節税効果とデメリットを天秤にかけ、慎重に判断しましょう。
二次相続を見据えた資産配分
最初の相続(一次相続)では配偶者控除により配偶者が取得した遺産は相続税ゼロで済むケースが多いです。しかし配偶者に資産が集中すると、いざ配偶者が亡くなった二次相続で子だけが多額の遺産を相続する形になり、結果的に高い税率が適用されてトータルの税負担が増えてしまうことが少なくありません。そこで、一次相続から子にもある程度遺産を渡しておくなど、一次・二次を通じて相続税負担を平準化する工夫が有効です。例えば遺産総額1億円で配偶者と子1人が相続人の場合、一次相続で全額を配偶者が相続すると二次相続までの総税額は約1,220万円になりますが、一次相続で配偶者5,000万円・子5,000万円と分けておけば総税額は約545万円で済んだという試算もあります。また、夫婦それぞれが生命保険に加入しておくと、一次相続・二次相続の両方で500万円×法定相続人の非課税枠が使えるため効果的です。高齢になってからの保険加入は難しい場合もあるので、余裕のあるうちに検討しておきましょう。
対策の第一歩:資産把握と専門家への相談
相続税対策の第一歩は、何と言っても現状の資産を正確に把握することです。預貯金や有価証券、不動産の評価額、保険の加入状況、借入金の残高などを一覧にまとめ、自分の家庭では将来相続税がかかりそうかどうかを試算してみましょう。仮に今のところ相続税の心配がなさそうでも、備えあれば憂いなしです。今後資産価値が上がったり、税制が変わって課税範囲が広がる可能性もあります。実際2024年には生前贈与加算期間の延長(3年→7年)など相続税制の改正が行われました。
その上で、必要に応じて税理士など専門家に相談することをおすすめします。相続税の経験豊富な専門家であれば、「現状のままだと相続税はいくらになり、対策すればどれだけ減らせるか」を具体的にシミュレーションしてくれます。例えば生命保険や不動産、生前贈与など複数の手段を組み合わせて最適なプランを提案してもらえるでしょう。税理士の実務支援経験から言えることですが、生前対策は各家庭によって有効な手段が異なります。専門家のアドバイスを活用しながら、計画的に進めることが効果的です。
50代の子世代にとっては、親御さんがまだ健在な今こそが対策を始めるチャンスです。資産の棚卸しや必要書類の整備、家族間の話し合いなど、できる準備から着手してみてください。専門家への相談も早めに行うことで、安心して将来に備えることができるでしょう。
相続税のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
本記事では相続税対策の基本ポイントについて、早めに準備する重要性や具体的な生前対策の方法をご紹介しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、相続税対策はもちろん、家族信託や遺言作成など相続に関する初回無料相談を承っております。将来に備えて何から始めればよいかわからない方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。