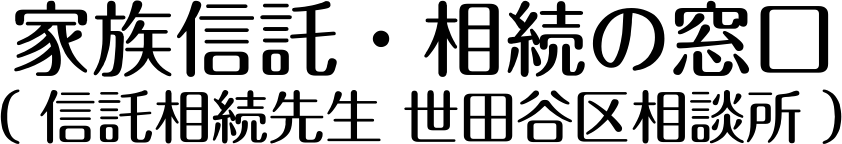未登記借地権の家族信託
- 公開日:
- 更新日:
背景と重要性
家族信託(民事信託)を活用した財産管理・承継対策が広まりつつあり、不動産を信託財産に組み入れるケースも増えています。その一例として、借地上に建つ建物を信託する際には、その土地を使用する権利である借地権も合わせて信託財産に含める必要があります。しかしながら、借地権が未登記の場合(未登記借地権)には、第三者に対する対抗要件や信託登記の可否といった特殊な法的問題が生じます。適切に対処しないと、信託後に第三者に対して借地権を主張できないリスクや、受託者の義務違反とみなされる恐れもあります。
本記事では、未登記借地権を信託財産とする家族信託に関わる法的論点と実務上の対応策について、司法書士・弁護士・税理士・不動産業者といった専門家の視点から丁寧に解説します。借地借家法10条や信託法14条・34条など関連法規とその趣旨を整理し、地主の承諾取得の実務ポイントや分別管理義務への対応まで、具体例を交えて体系的に説明します。借地権という複雑な権利を含む家族信託を安全かつ円滑に設計・運用するための指針を示します。
借地借家法10条:未登記借地権の第三者対抗要件
借地権の対抗要件と未登記借地権の基本
まず押さえるべき基礎として、借地権の第三者対抗要件があります。借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」を指します(借地借家法2条1号)。土地賃借契約に基づいて土地を使用収益する権利ですが、契約の当事者以外の第三者、例えば底地を取得した新たな地主や底地に抵当権を設定した金融機関などに対してその権利を主張するには対抗要件を具備しなければなりません。
通常、民法の原則では土地賃借権(債権)の登記によって第三者に対抗できるとされています(民法605条)。しかしながら、借地権の登記には地主の協力が必要であるため実務上は極めて稀です。そこで特別法である借地借家法が、借地権の対抗要件に関して特別の定めを置いています。それが借地借家法10条です。同条1項は次のように規定しています。
- 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる
つまり、借地権者が当該土地上に自己名義で登記した建物を所有している限り、借地権そのものに登記がなくても、新たな地主やその他の利害関係人に対して借地権の存在を主張できるということです。この規定により、実務上は多くの借地契約で土地賃借権自体の登記がなくとも、借地上の建物登記によって対抗力を確保する運用が一般的になっています。
なお、借地権には地上権(物権)と賃借権(債権)があります。地上権であれば譲渡・転貸が自由で登記請求権もありますが、土地賃借権(賃借権)の場合は譲渡・転貸に地主の承諾が必要です(民法612条1項)。実務上、借地権の大半は土地賃借権であり、家族信託において扱う借地権も通常は賃借権です。そのため本稿では賃借権としての借地権を前提に議論を進めます(譲渡に承諾が要る点にも後述する地主承諾の話が関係します)。
建物滅失時の注意点と対抗力の維持
借地借家法10条1項は「借地上の建物が存在し登記されていること」を対抗要件としています。したがって建物が滅失した場合、原則として借地権の対抗力は失われてしまいます。もっとも、同条2項により暫定的な救済措置が認められており、建物滅失の日付や再築予定である旨など所定の事項を土地上の見やすい場所に掲示すれば、滅失後も最長2年間は対抗力が維持されます。これは建物が無くなっても一定期間は借地権者を保護するための猶予制度で、この猶予期間内に建物を再建して登記すれば従前通りの対抗力を復活させることが可能です。
以上のように、借地権の対抗力は建物の存否や登記の状況に強く依存します。そのため家族信託のスキームにおいても建物登記の扱いは極めて重要となります。特に信託設定時に建物の所有名義人が委託者から受託者へと変わる場合(後述するように、建物を信託財産に組み入れる際には受託者名義に変更するのが通常です)、建物の適切な所有権移転登記を怠ると借地権の対抗要件を喪失しかねません。したがって、家族信託を組成するにあたってまず押さえておくべきは、この借地権の第三者対抗要件の基本と、建物登記の実務上の取扱いです。
信託法14条:信託財産の対抗要件と未登記借地権への適用
信託法14条の規定と趣旨
次に、信託特有の論点として信託法14条に注目します。信託契約によって財産を委託者から受託者に移転した場合、その財産が「信託財産に属する」こと(=その財産が信託の目的に組み入れられていること)を第三者に主張するには一定の公示が必要とされています。信託法14条はその対抗要件について、平たく言えば次のように規定しています。
- 登記または登録をしなければ権利の得喪および変更を第三者に対抗することができない種類の財産については、信託の登記または登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗できない。
これは、「本来その財産について所有権の得喪や変更を第三者に主張するために登記・登録が必要とされる場合には、信託による名義変更でも同様に信託の登記(または登録)を経なければ、その財産が信託財産であることを第三者に対抗できない」という趣旨です。典型例として信託法14条の念頭にあるのは、不動産・船舶・自動車・航空機・特許権など、公的な登録簿によって権利変動を公示することが制度化されている財産です。これらの財産は本来、登記(登録)を経なければ所有権移転等を第三者に主張できません。したがって信託による所有権移転の場合にも同様に信託登記(信託の登録)を要求するというのが信託法14条の趣旨です。
一方で、登記制度のない財産(現金や動産、登記制度に馴染まない債権など)については、信託法14条上の特別な公示要件は課されないと解されています。例えば現金や家財道具などの通常の動産、あるいは債権(※一部に債権譲渡登記が必要な例外あり)については、「当該財産が信託財産に属する」という事実を証明できれば、第三者に対してもその主張が認められると考えられます。ただし、後述するように実務上は受託者の固有財産と混同しないよう明確に区別して管理すること(分別管理)が結果的に第三者対抗の上でも重要になります。
未登記借地権への適用問題:肯定説と否定説
問題は、未登記の借地権(土地賃借権)を信託財産とした場合に、この信託法14条の対抗要件規定を適用すべきかどうかです。学説上は大きく分けて肯定説(適用あり)と否定説(適用不要)が論じられています。
肯定説の立場
肯定説の立場では、土地賃借権の信託も不動産に関する権利変動に準じると捉え、「借地権の譲渡」にあたる以上は本来の登記要件を満たすべきだと考えます。借地借家法10条により建物登記で第三者対抗力が認められる場合であっても、借地権自体の譲渡という権利変動それ自体は不動産物権の変動に類すると評価します。したがって、信託による借地権の移転も信託法14条の射程に入り、たとえ借地権そのものが未登記であっても何らかの形で信託登記(またはそれに代わる公示)を行わなければ第三者、例えば受託者の一般債権者や転得者に対抗できないと解釈します。肯定説に立った場合、借地権について信託登記等の公示を欠く限り当該財産が信託財産に属することを第三者に主張できず、ひいては信託財産の独立性(信託法25条)による保護も及ばない恐れがあります。実務的には、借地権単独ではそもそも登記できない以上、この立場に立つと「第三者に対抗できない不安定な信託」になりかねないとの指摘があります。
否定説の立場
これに対し否定説では、土地賃借権はあくまで債権であって形式的には民法177条の「不動産に関する物権変動」には該当しないと捉えます。借地権の対抗力については借地借家法10条で特則が設けられており、建物登記という公示方法によって既に対抗要件が充足されている以上、信託法14条のいう「登記をしなければ第三者に対抗できない財産」には当たらない、という考え方です。換言すれば、借地権はそもそも建物登記という対抗要件制度が法定されている特殊な権利であり、信託財産となった場合にも改めて信託登記を要しない(というより登記のしようがない)と解されます。否定説によれば、未登記借地権であっても建物の登記名義さえ受託者に移せば借地権の対抗力は従前通り維持され、信託財産として第三者に主張可能だと位置付けられます。また、借地権(賃借権)は譲渡に地主承諾が必要(民法612条)であり、家族信託で地位移転する際には地主も承諾という形で関与している(=事実上、公知の状態になる)以上、改めて登記による公示を求めるのは実情に合わないという実務的感覚も背景にあります。
統一的な実務取扱いは確立していない
現状ではこの論点について統一的な実務取扱いは確立していません。信託法14条の文言に忠実に厳格解釈すれば肯定説にも理がある一方、否定説も実態に即した合理的解釈として有力です。実務家としてはリスク回避のため肯定説を前提に対策を講じるのが無難でしょう。すなわち、信託設定後の借地権について登記による公示ができない以上、他の手段で信託財産であることを明確化しておくことが肝要です。この点は後述する分別管理義務(信託法34条)の話とも関わってきます。次の章では、信託登記ができない財産を巡る分別管理義務との関係を踏まえ、具体的な対応策を検討します。
信託法34条:受託者の分別管理義務と登記制度の役割
分別管理義務の概要(信託法34条)と登記できる財産
家族信託において受託者は、信託財産と自身の固有財産(および他の信託財産)を明確に分けて管理する法的義務を負います。これを分別管理義務と呼び、信託法34条1項に定められています。信託財産の独立性を確保し受益者の権利を保護するための重要な規定であり、具体的な分別管理方法は財産の種類によって異なります。
信託法34条1項各号では、財産の種類ごとに受託者が講ずべき分別管理の方法を定めています。登記・登録が可能な財産(不動産・船舶・自動車・株式など公的登録制度のある資産)については、信託の登記または登録を行うことが分別管理の方法とされています。例えば不動産であれば所有権移転登記に併せて信託登記(登記簿への信託の記録)を施す、車両であれば車検証への信託の登録を行う、といった具合です。受託者は信託契約成立後、速やかにそのような登記・登録を行い、自らの財産と区別された状態にしなければなりません。これは法律上の義務であり、信託契約で免除することはできません。万一怠った場合、受託者は分別管理義務違反を問われる可能性があります。
実務上も、「不動産を信託財産とする以上、登録免許税の負担があっても信託登記は必須である」と指摘されています。このように、登記・登録が可能な財産については、信託登記等による公示を行うことが受託者の法的義務であり、信託スキームの安定性を確保する上でも重要です。信託登記を施せば、その財産が信託財産に属することが第三者にも明らかとなり、同時に信託法14条が要求する対抗要件も充足されることになります。したがって信託財産に不動産等が含まれる場合、受託者は信託契約成立と同時か遅滞なく所定の信託登記を申請する必要があります。もし信託登記を怠れば、「第三者に信託財産であることを対抗できない」(信託法14条違反)状態となるだけでなく、受託者の分別管理義務違反にも問われ得る点に注意が必要です。
登記できない財産の場合と未登記借地権への示唆
一方、登記・登録制度が利用できない財産(動産や通常の債権、現金など)については、信託法34条1項に基づき物理的分離や帳簿上の区別によって管理することとされています。例えば金銭であれば信託専用の預金口座に預けて管理し、信託財産ごとに会計記録を明確に分ける、動産であれば「○○信託財産」などと明示したタグや標札を付けて他の物と識別する、といった方法です。要は、受託者固有の資産と混同しないよう客観的に区別可能な状態で管理することが求められています。
もっとも、登記できない財産については第三者対抗要件の問題が別途生じる可能性があるため、慎重な対応が必要です。例えば受託者が保管している現金100万円が実は信託財産だったケースを考えます。受託者の債権者がその現金を差し押さえた際、受託者側が「その現金は信託財産だから差押えは不当だ」と主張しても、現金が混同管理されていた場合には認められないという見解があります。債務者が都合よく「それは信託財産だ」と主張して債権者の回収を妨げる恐れがある以上、信託財産だということが客観的に明らかでないものについては第三者に対抗できないと考えられるからです。この例からも分かるように、登記できない財産については受託者固有財産と明確に識別可能な形で管理する(保管場所・管理方法を特定し、信託財産のみ分離して保有する等)ことが望ましく、受託者の債権者からの差押えに備える必要があります。
以上を踏まえれば、先の信託法14条の議論とも重なりますが、未登記借地権を信託財産とする場合には特に通常以上に慎重な分別管理策が求められると言えます。土地賃借権そのものは登記による公示ができない分、借地権が信託財産に属することを他の手段で明確化し、受託者の固有財産との混同を防ぐ責任があります。次章では、この点を踏まえ、未登記借地権を家族信託に組み入れる際の具体的な実務対応策を解説します。
未登記借地権を信託する際の具体的な実務対応策
以上の法的整理を踏まえ、未登記借地権を家族信託に組み入れる際には以下のような対策を講じることが推奨されます。登記できない権利であっても、可能な限り「その財産が信託財産である」ことの公示性・証明力を高め、関係者間で認識を共有してトラブルを予防することが重要です。専門家としては、安全策を講じて受託者の義務履行と信託スキームの安定性を確保する視点が求められます。主なポイントを順に解説します。
(1)借地上建物の信託登記と信託目録での権利明示
第一に、借地上の建物を信託財産に含め、受託者名義に所有権移転登記を行い、さらに信託の登記(信託目録の作成)を施すことが極めて重要です。家族信託契約で委託者(元の借地人)が借地上の建物も信託財産に指定した場合、信託設定と同時にその建物の所有権は受託者へ移転します。受託者となった人物は、遅滞なく建物の所有権移転登記手続きを行い、自身を所有者(受託者)とする建物登記簿に信託の登記を付加します。建物登記簿上に新設される信託目録には、受託者の氏名と肩書き(受託者である旨)、信託の目的や受益者の氏名、信託期間などが記載され、当該建物が信託財産であることが公示されます【4】。この建物の信託登記を行うこと自体、受託者の分別管理義務の履行として不可欠であるのみならず、借地権の対抗要件を維持する上でも大きな意味を持ちます。
すなわち、借地借家法10条の要件である「借地権者が登記された建物を所有していること」における「借地権者」は、信託によって受託者に地位が承継されます。そのため受託者名義で建物が登記されていれば、借地権の第三者に対する対抗力(権利主張力)も従前どおり継続します。仮に信託後に底地が第三者に売却された場合でも、新所有者(新地主)は建物登記簿で受託者が所有者である建物の存在を確認でき、結果として借地権の存続を否認することは困難です。建物の名義を受託者に移転し信託登記を施しておくことは、受託者が借地権者となった後も借地権を第三者に対抗する力を保つ上で必要不可欠な対応なのです。
さらに、建物の信託登記に伴い作成される信託目録において、その建物が建つ底地に関する借地権(賃借権)も信託財産に含まれていることを明示しておくことが望ましいです。通常、信託目録には信託の目的や受益者、信託期間など基本事項が記載されますが、借地権付建物を信託する場合には、信託財産の欄に土地の表示(所在地番・地目・地積など)を付記し、「委託者が有するその土地の賃借権(借地権)も本信託の信託財産に属する」旨を記載することで、「当該借地権も信託財産である」ことを公示しておきます。
信託目録は不動産登記簿の一部として誰でも閲覧可能なため、利害関係人に対し信託内容の重要部分を知らせる機能があります(もっとも一般に第三者に詳細な内容を知られたくない場合の配慮も必要ですが)。信託登記の際に上記のような記載を施しておけば、少なくとも関係者に対して借地権が信託財産に含まれている事実を認知させる効果が期待できます。
なお、借地権そのものの登記(借地権設定登記)は本ケースでは割愛しています。もし地主の協力が得られるなら、理想的には信託契約の締結前後に借地権の登記名義人を変更(新たに設定登記)しておくことも考えられます。しかし一般に地主は借地権の登記に消極的であるため、現実には困難な場合が多いです。そのため建物の信託登記と信託目録での権利明示という組み合わせで、借地権の信託財産性を担保するのが実務的な対応となります。
(2)信託契約の公正証書化によるエビデンス確保
第二に、信託契約自体を公正証書で作成しておくことも有用です。公正証書は公証人が関与して作成する公文書であり、契約当事者間の合意内容を強力に証明する効力を持ちます。家族信託契約書を公証役場で公正証書にしておけば、信託の成立および内容(未登記借地権が信託財産に含まれていること等)について将来第三者に示す際にも信用性が高まります。また原本が公証役場に保管されるため、契約書の紛失や改ざんリスクも軽減できます。信託が長期間に及ぶ場合でも、公証役場で正本・謄本を保管・再発行してもらえるため安心です。
特に未登記の権利を含む信託では、「いつ・どのような内容の信託が成立したか」という確定日付の証明が重要になります。万一、受託者の倒産時などに裁判所で「その財産は信託財産だ」と主張する際、公正証書の信託契約書があれば信託の存在と効力発生時期を直ちに立証できます。公正証書には公証人による確定日付が付与されるため、信託の効力発生日を巡る不要な紛争を防止する効果もあります。以上のように、信託契約書の公正証書化は信託内容の証明力・安全性を高める手段として強く推奨されます。
(3)帳簿管理の徹底と信託専用口座(信託口口座)の活用
第三に、受託者による財産管理の実態面から信託財産の独立性を明確にする工夫も不可欠です。未登記借地権の信託では、土地賃借権そのものに登記がない分、日々の管理状況に即して信託財産を区別する姿勢が重要となります。具体的には以下のような対応が推奨されます。
- 帳簿・記録の適切な作成: 受託者は信託財産に関する帳簿を整備し、借地権に関連する収支や状況を常に把握・記録します。例えば借地上の建物から生じる賃料収入、地主へ支払う地代、建物修繕費など、信託財産に関わる全ての金銭の流れを受託者固有の財産とは厳格に区別して帳簿付けします。科目も信託財産専用のものを設け、定期的に受益者や関係者へ収支報告することが望ましいです。
- 信託専用の銀行口座の利用: 金銭管理については、可能な限り信託専用の預貯金口座(俗に「信託口口座」と呼ばれるもの)を開設して活用します。金融機関によっては個人信託向けの信託口座を開設できる場合があり、口座名義に「〇〇信託」等と付記されることがあります。このような信託専用口座を用いれば、通帳や取引明細から見ても当該資金が特定の信託財産に属することが一目でわかるため、客観的な公示という観点からも望ましいとされています。仮に受託者の他債権者からその預金に差押えを受けた際にも、「当該預金は〇〇信託の信託財産である」という主張を裏付けやすくなります。
- 通常口座を使う場合の工夫: しかし、日本の金融実務では信託口口座の開設に非協力的な銀行も多いのが実情です。その場合、受託者個人名義で新規に開設した通常の銀行口座を一つ信託専用口座として充て、信託契約書や信託目録にその口座を「本信託財産の管理用口座」として明記しておく方法があります。重要なのは、信託財産に属する金銭を受託者固有の金銭と物理的・会計的に区別し、絶対に混同しないことです。例えば借地上の建物からの賃料収入がある場合には必ず信託専用口座に直接振り込ませ、地主への地代支払いも同口座から行う、といったルールを徹底します。そうすることで通帳上の動きを見ても信託財産の範囲が明確になります。また帳簿上でも信託財産の収支科目を独立させ、受益者への報告時にも当該信託財産固有の残高・収支を示します。こうした分別管理の徹底により信託法34条の義務を果たすと同時に、第三者から見ても当該財産が信託財産であることを主張・認識しやすい状況を作り出すことができます。
(4)地主の承諾取得と「借地権譲渡承諾書」の作成
第四に、借地権を信託する際は地主(底地所有者)の承諾を確実に得ることが大前提です。民法612条1項は賃借権の譲渡や転貸に地主の承諾を要すると定めており、信託によって借地権が受託者に移転する行為も形式的には「賃借人の交替」(賃借権の譲渡)に該当します。したがって、信託契約を締結する前に地主に事情を説明し、書面による承諾を得ておかなければなりません。もし承諾を得ず無断で譲渡した場合、地主は借地契約を解除することができるとされています(民法612条2項)。家族信託であっても譲渡禁止特約の適用除外にはならない点に注意が必要です。
地主が承諾しない場合の救済策として、借地借家法19条に基づく裁判所の許可制度(いわゆる借地非訟手続)があります。これは「借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合」に地主が不合理に承諾を拒むとき、借地人が裁判所に許可を求めることで、一定の条件下で承諾に代わる許可を得られる制度です。裁判所による許可が下りれば地主の承諾なしに譲渡が可能となります。なお、借地借家法21条により、19条の規定に反して借地人に不利な譲渡禁止特約は無効とされています。つまり契約上いかに譲渡禁止が謳われていても、建物譲渡(借地権譲渡)を伴う場合には法的に裁判所許可の道が保障されているわけです。
以上のように、最終手段として裁判所許可制度もありますが、手続には時間と費用を要するため可能な限り任意の承諾を取り付けるのが望ましいのは言うまでもありません。専門家としては家族信託スキームの設計段階から地主への説明・交渉も見据え、早期に承諾を得るべく適切に助言・対応することが重要です。
承諾料(名義書換料)の相場と交渉
地主の承諾を得る際に実務上問題となりやすいのが承諾料(名義書換料)の支払いです。一般に承諾料の相場は借地権評価額の約10%程度とされています。都心部など借地権評価額自体が高額なケースでは、仮に10%でも相当な金額となり得ます。ただし承諾料については交渉の余地もあり、状況次第では減額や免除が認められることもあります。
特に家族信託の場合、「財産管理のために親族に信託するだけで利用形態は今までと変わらない」という点を丁寧に説明し、地主の理解を求めることで承諾料を大幅に減額してもらえたケースや、免除してもらえる実例も存在します。実際、信託設定時の受益者が委託者本人(=元の借地人)であり、名義は受託者に変わっても借地上の建物の使用実態は従前どおりであることを強調すれば、地主にとっても実害がないとの安心材料になります。地主から見れば新たに見知らぬ第三者が借地権者となるよりも、事情を分かった従来の借地人とその家族が関与する方が心理的抵抗は小さいでしょう。承諾料の金額が高額で資金的に負担が大きい場合、代替策として任意後見契約や遺言による承継(遺言信託を含む)を検討に入れる手もあります(もっともそれらは信託ほど柔軟ではありませんが)。いずれにせよ、地主との交渉は信託組成前の計画段階から十分に行い、不要なトラブルを避けることが大切です。
承諾書に盛り込むべき内容
地主から口頭で承諾を得たら、必ず書面(承諾書)の形で確認を取ります。一般的に「借地権譲渡承諾書」などと呼ばれる書面で、今後の証拠として非常に重要です。承諾書には主に次のようなポイントを盛り込んでおくとよいでしょう。
- 当事者の明示: 現在の借地権者(譲渡人=委託者)と、新たに借地権者となる受託者(譲受人)の氏名・住所を正確に記載します。例:「譲渡人(現借地権者・委託者兼受益者)〇〇〇〇」「譲受人(新借地権者・受託者)〇〇〇〇」。
- 承諾の内容(範囲)の特定: どの行為について承諾するのか具体的に示します。通常は「借地権およびその目的たる借地上建物を信託契約に基づき受託者に譲渡(信託財産として移転)することを承諾する」という文言になります。さらに可能であれば、信託期間中の受託者変更や信託終了時に借地権が委託者に戻る場合も包括して承諾してもらうのが望ましいです。承諾書に「本承諾には、信託期間中に受託者が変更されその新受託者に本借地権が移転する場合、及び信託契約の終了により本借地権が譲渡人に再移転する場合を含む」等の一文を加えておけば、将来これら事態が生じても改めて承諾を得直す必要がなくなります。実際、信託終了によって借地権が受託者から委託者に戻る行為も法律上は譲渡に該当しますが、元の借地人に名義が戻るだけなので地主の心理的抵抗は小さく、承諾料も通常不要かごく低廉で済みます。初めから名義戻しを許容する包括承諾を得ておくのが理想的です。
- 借地契約条件の維持: 信託による譲渡後も従前の土地賃貸借契約の条件が一切維持されることを明記します。例:「本承諾は現行の土地賃貸借契約の地代、契約期間その他一切の条件を変更するものではなく、譲渡後も契約条件は全て従前通り維持される」。これにより地主・借地人双方が契約内容に変更がないことを確認できますし、地主にとっても不利益がないことが保証され安心感を与えられます。
- 受益者(元借地人)の使用継続の承認: 家族信託では形式上借地権者が受託者に替わった後も、実質的には従前どおり委託者兼受益者がその土地上の建物に居住・使用し続けるケースが大半です。そこで、受益者による建物使用を地主が承諾する条項も設けておくと安全です。例:「地主は、信託後も受益者〇〇(譲渡人)が本借地上建物を占有・使用することを承諾し、これが受益権の享受および受託者による管理行為の一環であって賃貸借契約上の無断転貸に該当しないことを確認する」。こう記載しておけば、受益者の占有が賃貸借契約上の無断転貸ではないことを明確にし、後日の紛争を予防できます。
- 建替え行為に関する取り扱い: 借地契約によっては、借地上建物の増改築や建替えに地主承諾を要する特約が定められている場合があります。信託期間中に建物の老朽化等で建替えの必要が生じる可能性も考慮し、建替えに関する承諾手続についても言及しておくと親切です。例えば承諾書に「本借地上建物の建替えについては従前の賃貸借契約条項に従うものとし、初回の建替えに限り地主は承諾料を請求しない」等の特約を入れるケースもあります(実際に盛り込めるかは個別交渉次第ですが、将来を見据えた合意事項として可能なら記載します)。万一承諾が得られない場合には裁判所の許可を求めることもできる旨(借地非訟手続の対象であること)に触れておくのも良いでしょう。
- 担保提供(融資)に関する承諾: 信託した借地権および建物を担保に金融機関から融資を受ける場合にも、地主の抵当権設定承諾が必要となるのが通常です。多くの金融機関が融資実行の条件として地主の承諾書提出を求めるからです。この抵当権設定承諾書(融資承諾書)は通常、金融機関所定の書式で別途取り交わします。信託を組む段階で将来的に借地上建物を担保提供して資金調達する可能性がある場合は、事前に地主にも相談しておくと安心でしょう。借地上の建物を担保にローンを受けること自体は可能ですが、地主承諾が得られないと融資は難しくなります(抵当権設定については裁判所許可制度は利用できません)。信託組成時に資金調達の予定がある場合、この点も踏まえて地主と合意を取っておきましょう。
- 承諾内容の限定明示: 承諾書の末尾には「本承諾は借地権の信託譲渡およびこれに付随する受託者変更等にのみ関するものであり、その他の契約条件や当事者の権利義務を新たに変更・制限するものではない」旨を明記します。これは承諾の効力が限定的であることを確認する条項です。本承諾書は家族信託に関連した譲渡・名義変更を許諾するだけで、従前の賃貸借契約上の地位や条件には一切影響を及ぼさないことを当事者間で確認します。地主にとっても「知らない間に契約内容を改変されるのでは」という不安を和らげる効果があります。
以上が承諾書に盛り込む主なポイントです。加えて承諾書には承諾日付や借地物件の表示(所在地、地番、地目、地積など)を正確に記載し、当事者が署名押印して正式な書面にしておきます。承諾書は後日の重要な証拠となる書類です。
地主の視点と承諾取得のポイント
最後に、地主側の視点も踏まえておきます。地主としては「この譲渡(信託)で自分に不利益やリスクはないか」が最大の懸念点です。そこで上記の承諾書の内容で、契約条件が変更されないことや受益者(元借地人)の使用継続を明示することで、経済条件は従前どおり・利用実態も変わらないと伝えることができます。特に受益者=元借地人が引き続きそこに居住・使用するケースでは、「これまでと同じ人が使うなら安心だ」と地主に思ってもらえる点が大きいです。無断転貸による知らない第三者が入るリスクもなく、信頼関係を保ちやすくなります。
次に、地代や借地料等の支払いの確実性も地主にとっては重要です。受託者が信託財産を管理するといっても、実質的な支払い原資は受益者の年金や賃料収入などに依存する場合が多いため、地代の滞納が起きないか心配されることがあります。交渉時には「信託後も従前どおり地代は確実に支払います。ご迷惑はお掛けしません」と約束し、必要に応じて信託契約書上で地代支払い遅滞時の措置(受託者の責任や解除条件など)を定めていることや、信託設定の目的(例:委託者高齢による認知症対策であること等)を説明して、地主の理解を得るよう努めます。このように地主にとって契約上の不利益や不安がないと示すことが、承諾取得のポイントとなります。
地主から書面承諾を得ておけば、少なくとも現地主に対しては家族信託に伴う借地権譲渡について後から異議を述べられる心配がなくなります。承諾書は後日の証拠となるだけでなく、地主自身が譲渡を認めた事実を示す重要書面です。将来地主が交代した場合(地主が底地を第三者に売却した場合など)でも、新地主は従前の賃貸借契約を引き継ぐ立場にあるため、原則として前地主の承諾も引き継がれると解されています。もっとも、新地主がその承諾書の存在を知らない可能性もあるため、信託期間が長期に及ぶ場合は承諾書の原本を大切に保管し、必要に応じ提示できるようにしておくべきです。承諾書で将来の受託者変更や名義戻しについて包括承諾を得ているとはいえ、念のため実際に受託者が交代する場合や信託終了時には地主(または新地主)へ事前に報告し、了承を再確認しておくのが望ましい実務対応です。そうすることで信頼関係を損ねず、円滑に地位移転が行えるでしょう。
家族信託組成から終了までの一般的な手順(まとめ)
最後に、未登記借地権を含む不動産を家族信託する場合の一般的な進行手順を簡潔に整理します。信託スキームを実行に移す際のチェックリストとして参考にしてください。
事前準備と調査
現行の借地契約書や不動産登記簿を入手・精査し、借地権の権利形態(地上権か賃借権か)、建物の登記名義、契約条件(地代、契約期間、譲渡禁止特約の有無など)を確認します。特に建物が借地人名義で登記されているか、土地賃借権に登記が付されていないか(未登記借地権か)を把握します。同時に、信託設定の必要性・目的(例:高齢の親の財産管理、円滑な相続対策など)を関係者で共有します。
地主への事前相談と承諾交渉
家族信託によって借地権を受託者に移転する計画について、地主に早めに説明し理解と協力を求めます。承諾書に盛り込む内容(上記ポイント)を提示し、必要であれば専門家から地主へ直接説明する機会を設けます。承諾料の金額や支払い条件についても交渉します。承諾が得られれば書面(承諾書)を取り交わし、将来の受託者変更や名義復帰(信託終了時)も包括して許諾を得ます。万一承諾料の支払いが困難な場合は減額交渉や、どうしても承諾が得られない場合は裁判所許可申立ても検討します。
信託契約書の作成・締結(公正証書化)
信託目的、当事者(委託者・受託者・受益者)、信託財産(借地権および借地上建物)、受益者の権利内容、信託期間、信託終了時の帰属権利者などを定めた信託契約書を作成します。借地権について地主承諾済みであることや、受託者の権限(賃借人としての権利行使)・分別管理方法(専用口座の使用等)も明記します。可能であれば公証人役場で契約を公正証書にし、契約内容と成立日時に確定的な証明力を持たせます。
不動産の名義変更登記と信託登記
信託契約の効力発生と同時に、不動産登記の申請を行います。具体的には借地上の建物について委託者から受託者への所有権移転登記を申請し、併せて信託の登記(信託目録の新設)も行います。信託目録には上記のとおり、借地権も信託財産に属する旨を記載します。登録免許税等の費用はかかりますが、受託者の分別管理義務の履行と借地権の対抗力維持のため必須の手続きです。地主承諾書が取得できていれば登記申請時に提出し(提出がなくても承諾書は必ず保管)、無事に登記識別情報等を受領します。
信託財産の移管と管理開始
登記手続きが完了し信託が開始したら、受託者は遅滞なく財産の分別管理を実行します。例えば金銭であれば信託専用の預貯金口座を開設して元の口座から信託財産分を移し替えます。借地上建物の賃貸人になっている場合は、借家人に対し賃料の振込先を新たな信託口座へ変更する通知を行います。地主への地代支払いも新口座から行うよう切り替えます。信託専用の帳簿(会計記録)を作成し、信託財産の収支・残高を管理します。受益者や関係人には定期的に管理状況を報告し、信託財産が適正に分別管理されていることを示します。
信託期間中の対応
信託期間中に建物の建替えや担保提供(融資)など特別な行為を行う場合、必ず事前に地主の承諾を得ます。また、受託者を交代する必要が生じたり(受託者の辞任・死亡等)、信託内容を変更する場合も、当初に取り付けた承諾書に基づき地主へ報告し了承を再確認します。万一地主が途中で交代した場合には、新地主に対して家族信託の趣旨と既存の承諾書の存在を説明し、引き続き契約関係の維持に協力してもらいます。受託者は常に忠実義務・善管注意義務(信託法27条・28条)を意識し、信託目的に沿って借地権および建物を適正に管理します。
信託終了時の手続
信託契約で定めた終了事由(例えば受益者の死亡や信託期間満了)が発生したら、信託を終了させます。借地権および建物は帰属権利者(信託終了後に権利を引き継ぐ者)へ移転させる必要があるため、受託者から帰属権利者への所有権移転登記(信託抹消登記)を行います。この際も法律上は借地権譲渡にあたるため、あらかじめ承諾書で包括承諾を得ていればスムーズですが、漏れていた場合は地主に追加の承諾を求めます(または裁判所許可を申請します)。信託財産に属する金銭も含め、残余財産を受益者または帰属権利者へ交付し清算します。最後に受託者から関係者へ信託計算書を交付するなど報告を行い、一連の信託事務を完了します。
以上のプロセスを丁寧に踏むことで、未登記借地権を含む家族信託でも法律上のリスクを抑えつつ円滑な財産管理・承継を実現することが可能です。借地権は権利関係が複雑で慎重な取扱いが必要な財産ですが、借地借家法や信託法の規定を正しく理解し、関係者間で十分な合意形成と証拠書類の整備を行うことで、安全かつ効果的な信託スキームを構築できます。本稿の解説が、専門家の皆様が現場で適切な判断と対応を行う一助となれば幸いです。