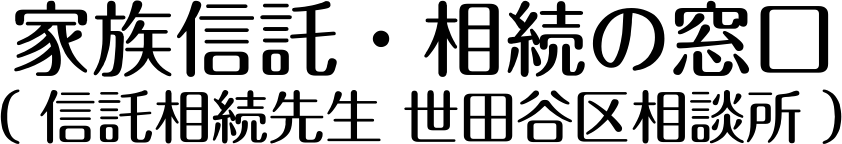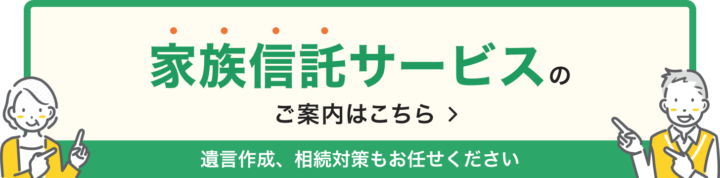家族信託のメリット・デメリットとは – 利用前に知っておきたいポイント
- 公開日:
- 更新日:
親が高齢になり、財産管理や相続について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。近年注目される家族信託は、親の財産を信頼できる家族に託すことで、将来の認知症対策や円滑な相続に備える仕組みです。家族信託を利用すれば、親が万一認知症になっても財産が凍結されずに済むなど、多くのメリットがあります。しかし一方で、手続きの手間や費用、家族間の調整など注意すべき点も存在します。本記事では家族信託の主なメリットとデメリットを専門家の視点も交えながらわかりやすく解説し、さらに家族信託が向いているケース・向かないケースについても紹介します。高齢の親を持つ50代の子世代の方が、家族信託を利用すべきか判断するための参考になれば幸いです。
家族信託の主なメリット
まず、家族信託を活用することで得られる主なメリットから見ていきましょう。家族信託は従来の遺言書や成年後見制度では実現できない機能を備えており、親の財産を守り活用する上で多くの利点があります。
認知症による資産凍結を防げる(財産管理の柔軟性)
家族信託最大のメリットは、親が認知症になって判断能力が低下しても資産を凍結させずに済む点です。日本では高齢者の約5人に1人が認知症になるとも推計されており、認知症は決して他人事ではありません。通常、親が認知症になってしまうと銀行口座が凍結されて預金を引き出せなくなったり、不動産を売却・処分するにも家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要が出てきたりします。しかし家族信託を親が元気なうちに組んでおけば、仮にその後親御さんが認知症になっても資産が凍結されず、子どもが財産の管理や必要に応じた処分をスムーズに行うことができます。例えば、親御さんが施設に入居して実家が空き家になった場合でも、信託で託された子どもが適切なタイミングで実家を売却し、その資金を介護費用に充てることも可能です。このように家族信託なら親の判断能力にかかわらず柔軟な財産管理が実現できるため、認知症による資産凍結対策として大きな効果を発揮します。
遺言書にはない機能(遺産承継の指定が可能)
家族信託には「生前の財産管理」と「遺言の機能」をあわせ持つ点も重要なメリットです。遺言書の場合、財産の分配は本人死亡後の一度きりですが、家族信託では信託契約の中で委託者(親)の死亡後、信託財産を誰に引き継ぐか指定することができます。これにより、遺言では難しい二次相続(親が亡くなった後さらに配偶者が亡くなった場合の承継先)まで含めて指定することも可能です。例えば「父から母へ財産を相続させ、その母が亡くなった後は長男へ引き継ぐ」といったように、世代を超えた承継先まで決めておくことも家族信託ならではの機能です。また、信託契約であらかじめ決めた受託者(財産を管理する人)がいれば、親が亡くなった後もその受託者が引き続き財産を管理・運用できるため、煩雑な遺産分割協議の手間を省けます。さらに、財産を受け継いだ配偶者や子ども自身が高齢だったり障がいがあったりして管理が難しい場合にも、信託なら信頼できる代理人(受託者)が継続管理できるので安心です。ただし注意点として、家族信託で管理していない財産(信託財産に含めなかったもの)は通常の相続手続きが必要になるため、別途遺言書も用意しておくほうが安全です。
家庭裁判所を介さず家族で資産管理ができる
成年後見制度(法定後見人)では、財産の処分や大きな契約を行う際に家庭裁判所の許可が必要となるなど、どうしても手続きに制約と時間がかかります。これに対し家族信託では、契約で定めた範囲内であれば家庭裁判所を介さずに家族(受託者)が資産を管理・処分できます。たとえば後見制度では自宅を売るにも裁判所の許可が必要ですが、家族信託なら契約で売却権限を定めておけば、受託者が必要に応じて迅速に売却して資金化できるわけです。この手続きの簡便さとスピードも家族信託の大きな魅力です。また、家庭裁判所の監督下にないため、家族の判断で資産運用の内容を柔軟に決められるというメリットもあります(ただし受託者には契約内容に従った忠実な管理義務があります)。結果として、心理的な負担やコストの軽減にもつながります。専門家も「家庭裁判所を通さずに済むことで、定期報告の負担や専門家後見人への報酬を省ける点は家族信託の大きなメリット」と指摘しています。
家族信託の主なデメリット
次に、家族信託を利用する際に知っておきたいデメリットや注意点を解説します。メリットの多い家族信託ですが、誰にとっても万能な制度ではありません。手続きや管理面での負担、家族間の合意形成など、事前に理解・準備すべきポイントがあります。
手続きの複雑さと費用負担(契約書作成や登記費用など)
家族信託の導入には複雑な手続きと一定の費用がかかる点に注意が必要です。家族信託を開始するには、家族間で十分に話し合って信託する財産や契約内容を決め、公正証書による信託契約書を作成し、不動産があれば信託登記の手続きを行うなど、やるべきことが多岐にわたります。これらは法律や税務の専門知識が求められる作業であり、契約内容によっては税金面の検討も欠かせません。そのため司法書士や弁護士等の専門家に依頼して契約書を作成するケースが一般的です。当然ながら契約書の作成費用(数十万円程度~)や公証役場の手数料、不動産の登記費用(登録免許税や司法書士報酬など)は利用者側の負担となります。加えて、信託を組むまでに家族での話し合いや資料準備など時間と労力も要し、開始まで数ヶ月かかる場合もあります。
このように、家族信託は気軽に始められる手段ではなく、手続きの煩雑さと初期費用の負担がデメリットと言えるでしょう。十分な準備期間と費用計画を持って臨むことが大切です。
信託財産の管理責任・手間がかかる
家族信託を始めると、受託者(財産を託された子ども等)には長期にわたる財産管理の責任と事務作業の負担が発生します。受託者は親に代わって財産を管理・運用する立場ですので、例えば預金の出し入れや不動産の賃貸管理、売却処理など日常的な財産管理を実行する必要があります。信託法上、受託者には善管注意義務や忠実義務、分別管理義務など厳格な義務が課されており、信託財産に関する収支の帳簿を作成して受益者に報告する義務もあります。さらに、不動産収入など信託財産から年間一定額以上の収益がある場合には税務署への信託計算書の提出など税務申告の手間も生じます。加えて、親が認知症を発症してから亡くなるまで平均5~10年と言われる中、その間ずっと受託者が財産管理を続ける必要があり、信託の運用は長期に及ぶ可能性があります。つまり家族信託は一度契約して終わりではなく、その後の管理に労力がかかる点を理解しておく必要があります。受託者となる家族には「親のためとはいえ、自分が長期間その役割を担う覚悟」が求められるでしょう。信託の内容次第では帳簿作成や報告を簡素化する工夫もできますが、それでも受託者の負担がゼロにはならない点はデメリットとして押さえておきましょう。
家族内の理解不足によるトラブルの可能性
家族信託は親(委託者)と子どもの代表1名(受託者)だけで契約を結ぶことも可能です。しかし、他の兄弟姉妹や親族に十分説明せず進めてしまうと、「自分の知らないところで財産管理を任せている」「自分は信頼されていないのか」といった不満や不信感を招き、家族内のトラブルに発展する恐れがあります。特に特定の子どもだけが受託者となり親の財産を動かせる立場になるため、他の兄弟が疑心暗鬼になったり、後から「財産が勝手に使われたのでは」と揉めたりするケースも現実に起こり得ます。家族信託を円満に活用するには、契約当事者以外の家族にも信託の目的や内容をきちんと共有し、納得を得ておくことが重要です。もし家族間で信託に対する理解や信頼関係が十分でない状態で始めてしまうと、せっかく親のためを思って組んだ信託が逆に「争族」状態を招くリスクもあります。家族全員で信託の必要性を話し合い、できる限り合意形成してから開始するようにしましょう。
また、家族の中に信頼できる適任者がいない場合も無理に家族信託を結ぶべきではありません。受託者に悪意があれば財産を横領してしまう可能性もゼロではないからです。そうした場合には、成年後見制度(第三者の専門家後見人に頼る)や信託銀行のサービスなど、他の方法を検討するほうが安全なこともあります。家族信託はあくまで家族仲が良好で信頼関係がしっかりしているケースにこそ適した制度です。逆に「家族に任せるのは不安…」という気持ちが拭えない場合は無理に活用する必要はありません。そのような状況では他の方法(成年後見制度や財産管理委任など)による財産管理・相続対策を専門家と相談してみましょう。
家族信託が向いているケース・向かないケース
続いて、家族信託の利用を検討する際にどんなケースに適しているか、逆に適さないかを具体的に見てみましょう。家族信託は万能ではないため、家庭の状況や財産内容によって向き不向きがあります。以下に代表的なケースを挙げますので、判断材料にしてください。
向いているケース:親が認知症になる前に備えたい場合
将来的に親の認知症発症リスクに備えたい場合、家族信託はとても有力な選択肢です。前述の通り、認知症による口座凍結や資産凍結は誰にでも起こり得ます。親御さんがまだ判断能力のしっかりしている今のうちに信託契約を結んでおけば、万一将来認知症になっても財産管理の手続きを事前に整えておけるからです。家族信託契約は本人に判断能力があるうちしか締結できません。認知症を発症してしまってからでは手遅れとなり、結局成年後見制度を利用せざるを得なくなります。そうなると親族の負担も大きく、財産の柔軟な活用も難しくなってしまいます。「まだ大丈夫」と思えるうちから早めに備えることこそ家族信託成功のポイントです。特に、「最近親の物忘れが増えてきて心配だ」という場合は、早めに専門家に相談して信託の準備を始めることをおすすめします。認知症対策として家族信託は早く始めるほど効果を発揮するケースだと言えます。
向いているケース:複数不動産など資産管理を任せたい場合
親御さんが複数の不動産や金融資産を所有しており、その管理や処分を子どもに任せたい場合も家族信託が適しています。財産が自宅だけでなくアパートや駐車場、複数の土地など多岐にわたると、高齢の親自身で管理するのは大変です。家族信託を使っておけば、受託者となった子どもが親に代わってそれら資産を一元的に管理・運用できます。たとえば賃貸不動産があるケースでは、信託契約で子どもに家賃収入の管理や建物の維持修繕、必要なら売却といった判断まで任せることができるため、資産の有効活用がスムーズになります。また不動産が複数ある場合、将来の相続時に共有名義になると管理が複雑になりがちですが、信託によって管理権限を特定の受託者に集中させておくことで共有不動産のトラブルを避けられるメリットもあります。さらに、信託契約に「どの資産をどう管理・処分してよいか」を細かく定めておけば、子どもが柔軟に資産組み換えや売却による資金化を行い、親の生活費や介護費用に充てることも可能です。このように資産ボリュームが大きかったり管理が煩雑なご家庭ほど、家族信託によって資産管理を任せる効果が高いケースと言えるでしょう。
【向かない】親の財産が預金のみの場合
親の財産が預貯金のみで、不動産や自社株などがない場合には、無理に家族信託を利用しなくてもよいケースがあります。
近年、一部の銀行では、事前に手続きをしておけば子どもなどが親に代わって預金の引き出しや振込ができる「代理人届」や「代理人カード」といった制度を無償で用意しています(名称や内容は金融機関ごとに異なります)。これらの制度を活用すれば、万が一親御さんが認知症になっても一定の範囲で口座からお金を動かせるため、最低限の資金管理は継続できます。
したがって、預金凍結への備えだけを目的に家族信託を利用するのは安心感があるものの、信託契約の手間や費用とのバランスを考えると必ずしも得策とは言えません。預貯金のみの場合は、これらの制度も含めて他の方法を検討してみることをおすすめします。
向かないケース:家族間の信頼関係に不安がある場合
家族間の信頼関係に不安がある場合は、残念ながら家族信託には向きません。家族信託はその名の通り「家族に信じて託す」制度であり、受託者となる家族を信頼できることが大前提です。もし「任せたい子どもがいるが、他の兄弟がそれを快く思っていない」「家族内で財産に対する考え方が大きく異なる」などの状況があると、信託契約後にトラブルが発生するリスクが高まります。家族内の誰か1人に権限が集中すると、他の人が不信感を抱く恐れがあるのは前述の通りです。また、受託者が悪意を持っていれば財産を横領してしまう可能性もゼロではありません。もし信頼できる適任者がいない場合は、無理に家族信託を結ばず成年後見制度(第三者の専門家後見人に任せる)や信託銀行のサービスを検討するほうが安全なこともあります。家族信託はあくまで家族仲が良好で信頼関係がしっかりしているケースに適した制度です。逆に言えば、「家族に任せるのは不安…」という気持ちが拭えない場合は無理に活用する必要はありません。そのような状況では他の方法による財産管理・相続対策を専門家と相談してみましょう。
まとめ(メリット・デメリットを踏まえた検討のすすめ)
家族信託は、高齢の親を持つご家族にとって認知症対策や資産承継を柔軟に行える有力な手段です。メリットとして、認知症による資産凍結を防ぎながら生前から財産管理や承継先の指定ができること、そして家庭裁判所を通さずにスムーズな資産運用ができる点は大きな魅力でしょう。一方で、導入時の手間や費用、受託者に課せられる長期にわたる責任負担、そして家族内での合意形成といったデメリットも見逃せません。大切なのは、これらメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分たち家族の状況に家族信託が本当に適しているか検討することです。
本記事で紹介した向いているケース・向かないケースも参考に、ぜひ一度ご家庭の事情と照らし合わせてみてください。家族信託は決して万能薬ではありませんが、条件が合致すれば他の制度にはない大きな効果を発揮します。デメリットの章で挙げたようなリスクも、事前に対策を講じることで十分回避可能です。もし家族信託に少しでも興味があれば、早めに専門家(司法書士や弁護士など)へ相談し、メリット・デメリットを踏まえた最適なプランニングを提案してもらうと安心です。
最後にまとめとして、家族信託は高齢の親御さんの財産管理・相続対策に有効な手段ですが、利用前にそのメリットとデメリット、注意点をしっかり把握しましょう。そして家族全員の理解と協力のもとで進めることが成功の鍵です。適切に活用できれば、親御さんに万が一のことがあっても財産が凍結されず、残されたご家族が安心して暮らせる未来を築く助けとなるでしょう。
家族信託のご相談は世田谷区家族信託・相続の相談所へ
家族信託のメリット・デメリットや注意点について詳しくご紹介しました。世田谷区家族信託・相続の相談所では、家族信託を含む財産管理のご相談や相続対策のご提案を初回無料で承っております。本記事で取り上げた向いているケース・向かないケースも踏まえ、お客様のご家庭に最適な方法を専門家がアドバイスいたします。家族信託にご興味をお持ちの方、利用を検討中の方は、ぜひ当相談所までお気軽にお問い合わせください。